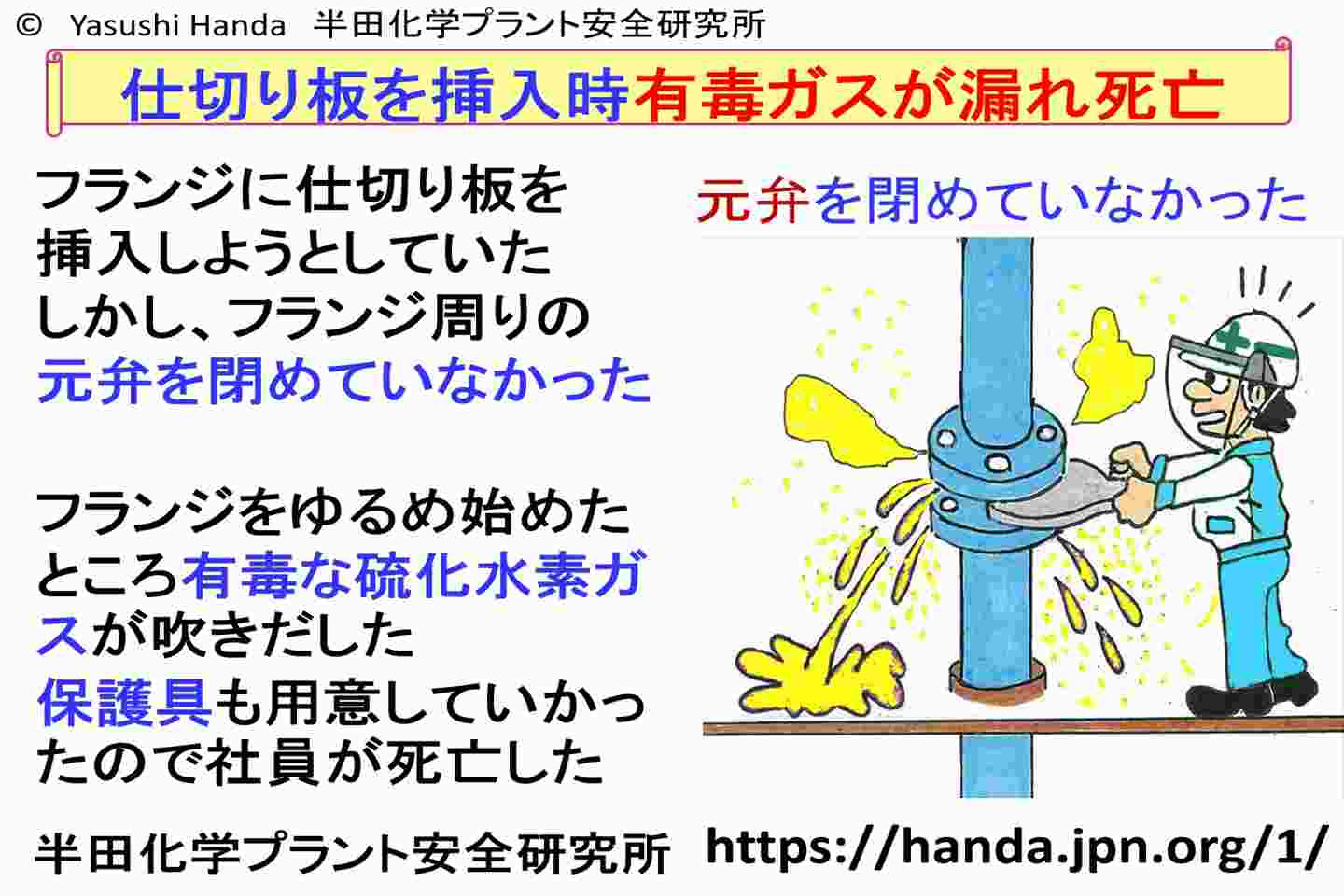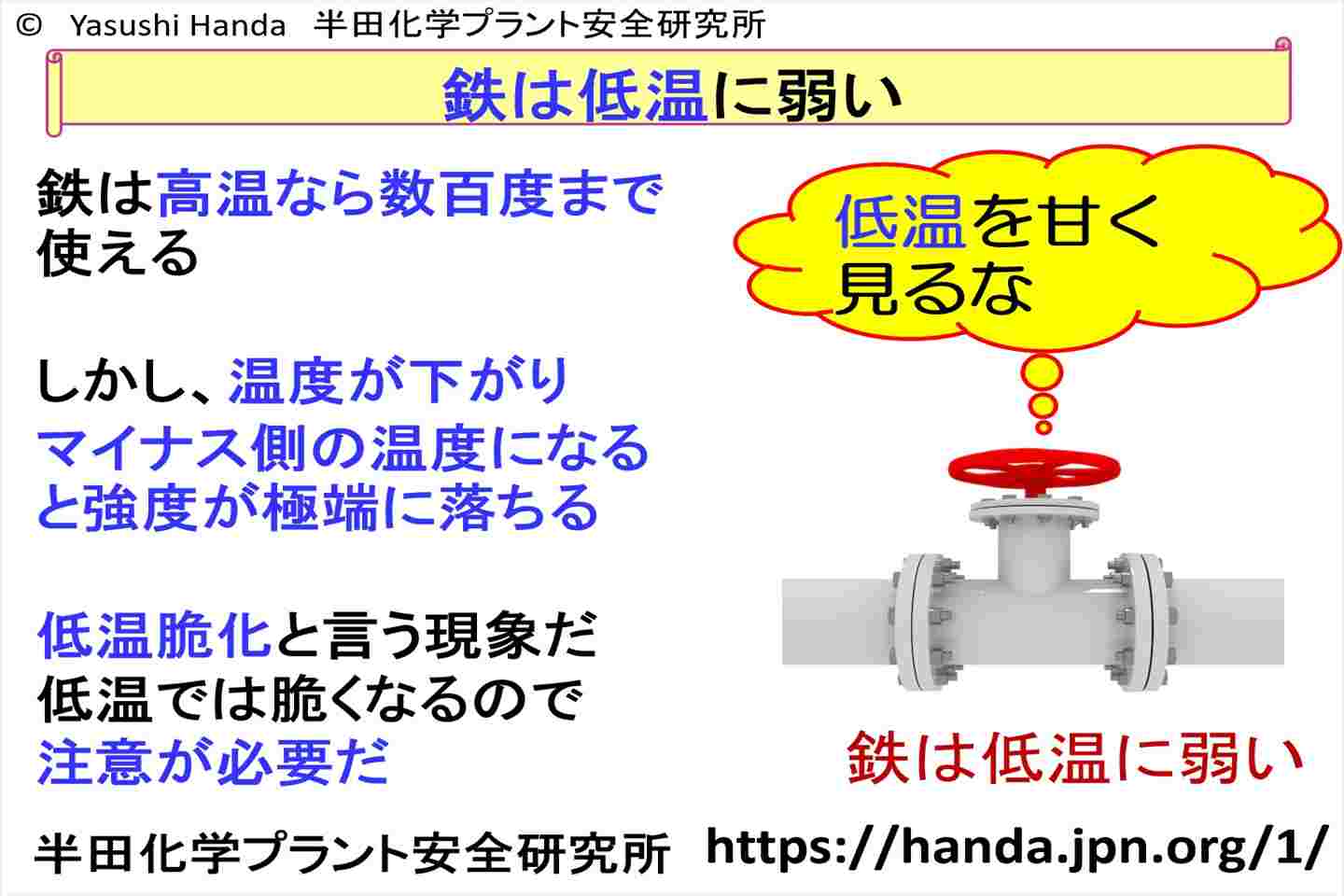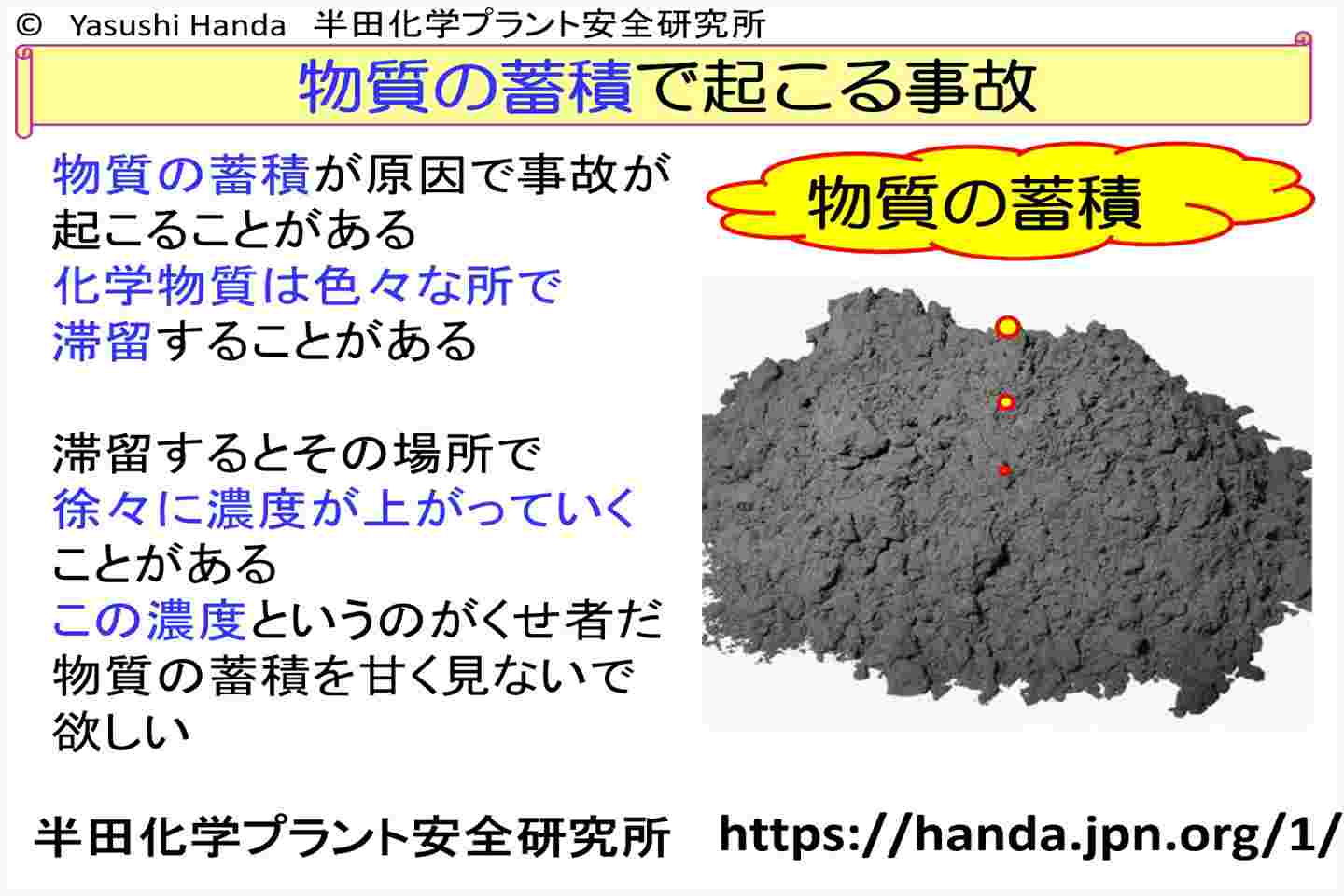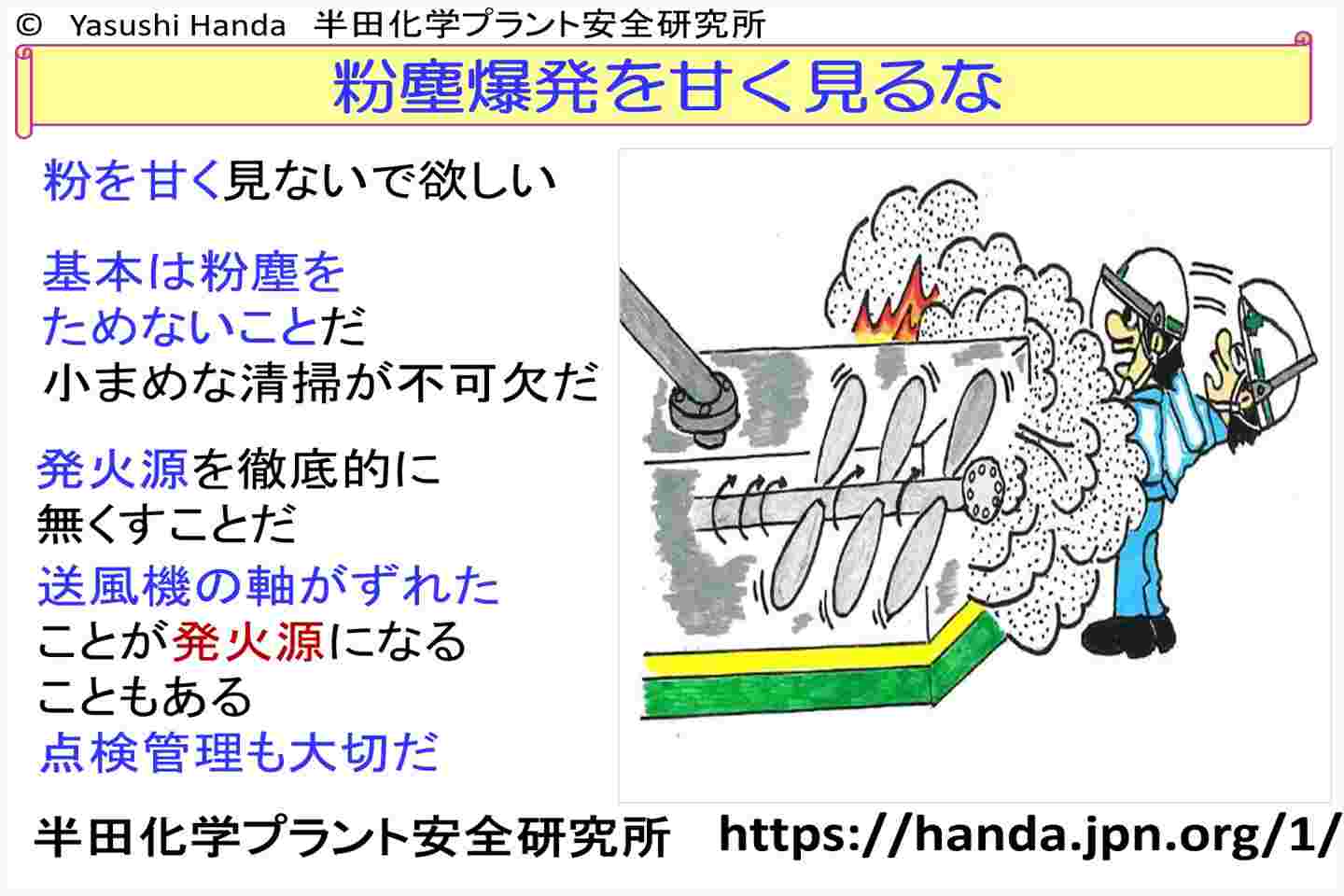ダブルブロック 失敗 1969/8/24の事故だ
千葉県にある酸化エチレンプラントの事故だ。スタート時窒素パージ中に空気の漏れ込みによる事故だ。
ダブルブロックで安全を確保する方式だったのに、運転員が弁を片方締めておらず空気が漏れ混んで爆発混合気ができ爆発した事故だ。
空気の漏れ込みで、酸素計の指示が上がっていたのに,安易に計器の誤作動だと思い込んで起きた事故でもある。
ダブルブロックで設計されていても、運転員が設計思想通りに2つの弁を同時に操作しなければ事故は起きると言うことだ。
ダブルブロックだから大丈夫だというわけではない。人が二つとも弁を閉めない限り、正しく機能はしない
ダブルブロックの安全思想が、運転にはうまく教育できていなかった事例だ
ダブルブロック方式だから、絶対安全だと思わないで欲しい。運転員が、片方の弁しか操作していなければ、機能し無いということだ
1986/1/21にやはりダブルブロックがうまく運用されず事故が起きている
この資料を見て欲しい 出典失敗百選 http://www.shippai.org/fkd/cf/CC0000113.html
出典:カーボンニュートラル燃料技術センター事例20
https://www.pecj.or.jp/japanese/safer/case_list/pdf/accident_00020.pdf
https://www.pecj.or.jp/japanese/safer/case_list/pdf/accident_00020_s.pdf
製油所で加熱炉昇温作業中、燃料ガスが漏れ込み炉内爆発した.防護壁壊れ通行中の作業員負傷--鉄製壁が9m吹き飛び、耐火レンガが半径30mの範囲に飛散した事故だ
ダブルブロックだから安全だとは言えない事故だ。安全のためバルブは2重化し、マニュアルでもパイロットバーナー点火時はメインバーナー側のバルブはダブルブロックすることと定めていたが、それを守らなかった事故だ
燃料バルブをダブルブロックすべき所のバルブを下流側だけしか閉としなかった。
わずかに漏れていた燃料ガスで点火時に爆発。窒素置換を終了し触媒再生作業のため加熱炉のパイロットバーナーを順次点火していたところ、突然加熱炉内で爆発
マニュアルでは、9本あるパイロットバーナーに点火を完了後、メインバーナーのガスライン(バルブは漏れ防止の為2重化され直列に2個設置されていた)のバルブを開けてメイン側バーナーに点火することになっていた。
しかし、これを守らずパイロットバーナーのガスラインを生かした時、メインバーナー弁をダブルブロックしておらずわずかに漏れがあり、メインバーナーからガスが炉内に漏れ込んでいた。これを知らずにパイロットバーナーに順次点火していた所9本目で爆発した事故だ
安全設計がなされていても、設計思想を理解して運転員が正しく操作しない限り事故は起こる
HAZOPでも見て欲しいのは、ハードとソフトがきちんとできているかを見て欲しい。
運転マニュアルの充実度、教育状況などソフトの面で問題がないかHAZOPでも見て欲しい